

近時、地球規模の課題とその達成目標を示したSDGsがますます注目されています。アンダーソン・毛利・友常法律事務所は、法律家として、いかにSDGsの達成に貢献できるかを模索し続けています。 当事務所は、クライアントの持続可能な成長に向けた法的課題をあらゆる角度からサポートすべく、各専門分野における弁護士がSDGsに関する知見を深め、サステナビリティ法務のベスト・プラクティスを目指します。
本特集では、SDGsに関する当事務所の取組みをご紹介すると共に、サステナビリティ法務に関する継続的な情報発信を行ってまいります。
本特集の第2回では、東京大学名誉教授(専門分野:国際法、国際経済法)であり、当事務所の客員弁護士でもある中川淳司氏にインタビューを実施しましたので、その様子をご紹介いたします。
※インタビュー実施日:2022年2月10日オンラインにて実施。
バックナンバー
【第2回】中川教授とビジネスと人権について考える
(東京大学名誉教授/当事務所客員弁護士・中川淳司×パートナー弁護士・龍野滋幹)
目次
Q1:近年、特に人権問題が重要視されている背景
龍野SDGsの意義及び直近の動向に関する対談に続いて、第2回目の今回は、ビジネス法務の世界で話題になっている「ビジネスと人権」について、国際経済法がご専門の中川淳司先生にお話を伺いたいと思います。よろしくお願いいたします。
早速ですが、ビジネスにおいて人権が重要であることは以前から変わらないと思います。近年、特にこの問題が重要視されているのは、どのような背景からでしょうか?
中川そもそも論から申し上げますと、これまで、人権保障は、国家の義務でした。日本国憲法は、人権を保障するのは国家の義務である、と定めています。国際人権条約においても、人権を保障するのは国家の義務とされてきました。
ところが、ここ20年くらいの間に、企業活動が人権に与える悪影響について、社会の関心が集まるようになりました。グローバル企業の人権侵害をウォッチするNGO(非政府組織)が人権侵害の事例を指摘しますと、SNSなどのソーシャルメディアであっという間に世界中に拡散します。企業にとっては、不買運動が起きる、株価が下がる、取引先を失うなど、重大なリスク要因になるのです。1997年に、インドネシアとベトナムにあるナイキの製造委託先で児童労働をさせていたことをきっかけとして、不買運動が起きました。その後も、似たような事例がしばしば問題になっています。これが、企業がビジネスと人権を軽視できなくなった背景です。
国際的な潮流としては、2011年に、国連の人権理事会で「ビジネスと人権に関する指導原則」(United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights)が決議されました。この指導原則には、企業は人権Due Diligence(人権DD)を実施するべきである、と書いてあります(第17原則)。そして、いま、欧州を始めとして、人権DDの実施を国内法として制定する動きが加速しており、日本企業もこの動きを無視できなくなってきています。
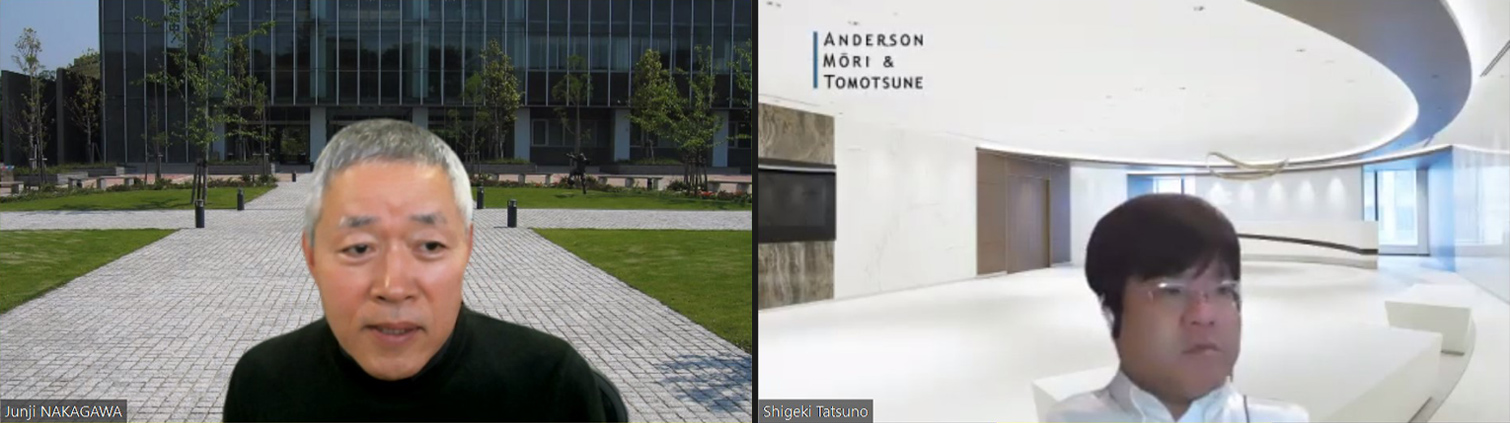
Q2:ビジネスと人権に関する指導原則
龍野これまでの企業法務の世界では、「会社は株主のものである」という伝統的株主資本主義とでもいうべき考え方が主流でした。ところが、近年では、「会社は社会的存在であって、様々なステークホルダーに支えられてこそ存在できる」という考え方が広がってきています。
中川企業の社会的な責任(Corporate Social Responsibility:CSR)のうち、特にS(Social)が人権尊重ということになるのですが、現在は、企業の人権尊重に関する国際的なルールが、法的拘束力のないソフトローとして広まりつつあるタイミングです。そして、欧州から始まった企業の人権尊重の責任をハードローとして法制化していく動きが徐々に拡大していく情勢だと理解しています。
龍野国連の指導原則の成立がブースター(後押し)になっているということでしょうか?
中川はい、指導原則が最も大きな転換点だと思います。指導原則が採択されたバックグラウンドを少しお話ししますと、国連は、1970年ころから、多国籍企業のCode of Conduct(行動指針)を制定して、特に先進国企業による途上国での行動をコントロールしようとしてきました。ところが、この試みは、先進国の反対によって挫折してしまいます。
2000年代に入ると、「国連グローバルコンパクト」(United Nations Global Compact)が策定されました。グローバルコンパクトは、アナン事務総長のときに、人権、労働、環境、腐敗防止など10の原則を打ち出し、グローバルコンパクトの参加企業はそれに沿った行動をして発表するという緩やかな動きでした。この動きは、現在も続いています。
このグローバルコンパクトの動きを支えたのは、ハーバードビジネススクールのジョン・ラギー(John Gerard Ruggie)教授です。ラギー先生は、2005年には、「人権と多国籍企業」に関する国連事務総長特別代表に選ばれました。
特別代表であるラギー先生は、2008年に、ビジネスと人権に関するフレームワーク「保護、尊重及び救済の枠組み」(Protect, Respect and Remedy: a Framework for Business and Human Rights)を提出しました。そして、2011年6月には、国連の人権理事会で、この枠組みを運用するための指針として、先ほど述べた「ビジネスと人権に関する指導原則」が承認されるに至ったのです。指導原則には、企業が人権を尊重する責任を負うことに関する、かなり細かい内容が書き込まれています。
Q3:人権DD重視の潮流
龍野指導原則は、人権尊重に関する企業のコミットメントや人権DD、さらには救済手続についても定めています。中でも、人権DDについては、第17原則から第21原則までの5項目にわたって、明示的かつ詳細な記載がなされています。
中川指導原則の肝になるのは、第17原則で述べられている人権DDだと思います。人権DDをひとことで申し上げますと、企業活動が人権に及ぼす悪影響を評価して、適切な対策を定めて実行するという一連のプロセスを指しています。M&Aの世界で耳にするDDが案件ごとのプロセスであるのに対して、人権DDは企業活動において継続的に実践するプロセスの問題なのです。
そして、指導原則は、人権DDのポイントになるコンポーネント(構成要素)を、第18原則から第21原則として記載しています。第18原則では、人権への実際の悪影響や潜在的な悪影響を推し量って評価すべきこと、第19原則では、評価の結論を踏まえて適切な措置を取るべきこと、第20原則では、事業活動で生じた悪影響への対応措置が十分だったかどうかを追跡調査すべきであること、第21原則では、こうしたすべてのプロセスを対外的に公表すべきであることをそれぞれ明記しています。これらは、企業活動における人権保護について、一連のPDCAサイクルを実施せよ、という意味です。
龍野指導原則自体はソフトローですが、2011年以降の10年くらいの間に、欧米中心とする各国でハードローとして立法する流れになっています。人権について欧米、特に欧州での動きが速いのは、どのような理由によるものでしょうか?
中川市民革命を経験した欧州には、もともと、人権保障の本家本元であるという源流があり、人権NGOの活動の本拠地でもあります。欧州には、人権尊重に対する文化的社会的なプリファランス(preference)があるのです。中でも、EU構成国は、いわゆるEU新指令(案)(The Commission on corporate due diligence and corporate accountability(案))の影響もあって、人権DDの国内法制化を積極的に進めようとしています。実は、この動きには、産業政策的な要素もあります。すなわち、欧州市場における人権尊重の基準を高くすることによって、欧州域外の企業にも域内企業と同様に高いハードルを課して競争条件を平準化するとともに、ゆくゆくは欧州の人権尊重基準を世界標準にしよう、という狙いです。人権に限りませんが、欧州は、まず欧州基準を作って、次にそれをグローバルスタンダードにしようと動くのが得意です。
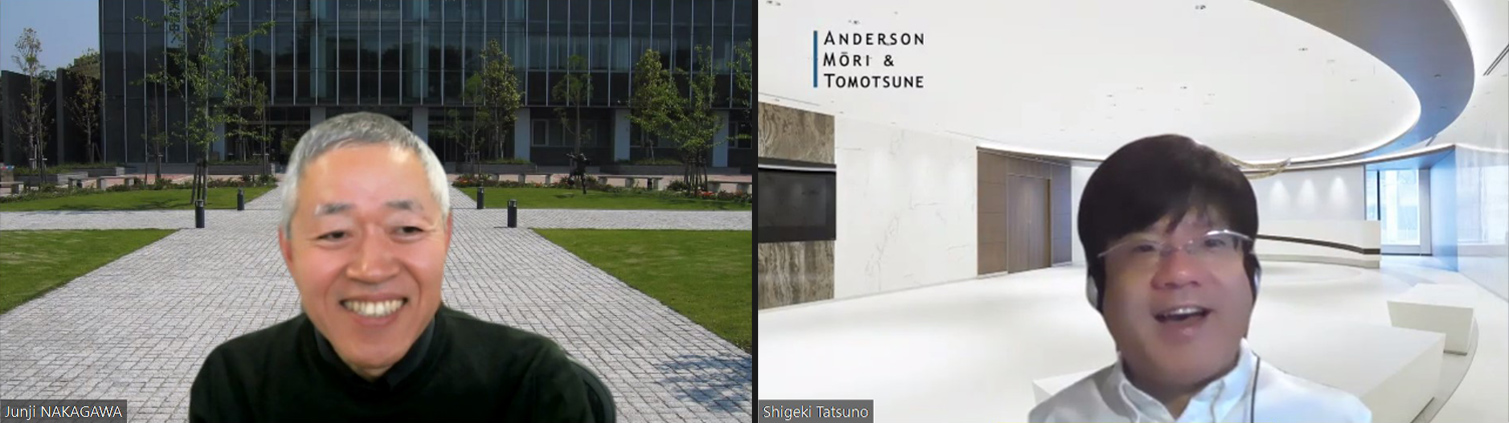
Q4:人権に関する日本の動向
龍野産業競争的に見ると、人権DDのハードロー化には、ある種したたかな側面があるのですね。日本の動きはいかがでしょうか?
中川日本政府も、本腰を入れ始めたところです。日本では、2020年10月に、「ビジネスと人権」に関する行動計画が策定されました。この行動計画においては、企業活動における人権DDの導入促進への期待が表明されており、人権DD導入の動きがあることを周知するとされています。つまり、日本政府は、人権DDの重要性を企業に知らせ、人権DDを実行することに期待を表明はするが、法的には拘束しないという考え方です。人権DDは負担になるのですぐには動けないという企業側の状況を踏まえ、企業にそれをあまねく義務付けまでするのは適当ではないのではないか、という考え方を表わしたものであるともいえます。また、2022年夏をめどに、日本政府が人権DDのガイドラインを作るというニュースもあります。
欧州を中心に人権尊重がグローバルスタンダードになりつつある中で、この行動計画を踏まえた日本企業がどのように振る舞うのか、今後、大いに注目すべきでしょう。
龍野経団連(日本経済団体連合会)は、2021年12月に、「企業行動憲章 実行の手引き」の「第4章 人権の尊重」を改訂するとともに、「人権を尊重する経営のためのハンドブック」を公表しましたが、様々な意見があって拘束力のあるルールにまではなっていません。日本における進捗について、先生のご評価はいかがでしょうか?
中川率直に申し上げて、現時点においてはまだ高い評価まではできないと思いますが、1つのトレンドとして、我が国でも人権DDへの取組みが進みつつあるのは確かです。
経済産業省と外務省が、2021年11月に公表した「日本企業のサプライチェーンにおける人権に関する取組状況のアンケート調査」は、上場企業2786社を対象として760社が回答したものですが、回答企業の7割が人権保護方針を策定していると答え、また、回答企業の5割強が人権DDを実施していると答えています。さらに、回答企業の7割が人権保護方針の策定にあたって、国連の指導原則を参照していると答えています。つまり、日本でも、回答企業の約半数が、国連の指導原則に則った人権保護に取り組んでいることになります。
売上の規模が大きく、海外での活動割合が高い企業ほど人権保護に取り組んでいます。特に、欧州でビジネスをしようと考えている企業にとっては、人権DDは絶対に対応しなければならない課題です。いまや、グローバル企業は、サプライチェーンにセンシティブにならざるを得ず、プロアクティブに人権DDに取り組まざるを得ないのです。もっとも、これは、グローバルにビジネスを展開している大企業の動きですから、中小企業における対応は、まだまだこれからだと思います。
龍野日本企業に課される課題は重いですね。
中川グローバルスタンダードとして国連の指導原則があり、今後は、ハードロー化の動きが全世界でさらに広がっていくと予想しています。アジアでも、2019年には、タイがビジネスと人権に関する指導原則に基づく行動計画を発表しています。今後は、新興国に進出する場合であっても、人権保護を強く意識せざるを得ないでしょう。
先ほども申し上げましたように、人権保護の問題は市民社会の関心が高く、常にNGOがウォッチしています。侵害事例は、あっという間に拡散しますので、対応を怠ることができません。企業は、人権保護はグローバルな事業活動のための投資であると考え、トップレベルの経営課題として取り組むべきでしょう。そして、人権保護に取り組むにあたっては、ネガティブキャンペーンをされたら困るというリスク的な発想だけではなく、取組みが取引先や投資家から評価され、また、求人や採用においても高評価がなされるというポジティブな面を捉えるべきであろうと思います。
龍野人権保護は、企業がビジネスを行うにあたっての新たな重要経営課題の1つですね。ありがとうございました。

次回は、「ビジネスと人権(その2)」として、人権DDなどにおける実務的な課題を取り上げます(3月中旬ころ掲載予定)。
