
AMT戦略的カーブアウトM&A ~各種法分野における実務上の留意点~
「事業ポートフォリオの最適化」が上場会社に求められる経営課題の一つとして定着しつつあります。その中で、カーブアウトM&A、すなわち、企業の特定事業を切り出した上で他社に対して承継させるM&Aは、その件数および規模ともに拡大を続けています。 一方で、カーブアウトM&Aの準備および実行に際しては、通常のM&Aとは異なり、多岐にわたる論点や留意点が数多く存在し、これらを十分に把握したうえでプロジェクトに臨むことが必要不可欠といえます。

座談会:エネルギー・トランジションの最前線【第3回】国内再生可能エネルギー市場の最新動向-蓄電池、風力、再エネM&A等を中心に-
第1回の「エネルギー市場に関する世界の潮流と日本企業の海外展開」、第2回の「国内再生可能エネルギー市場の最新動向-太陽光発電を中心に-」に続き、本シリーズ最終回となる今回は、国内エネルギー市場における蓄電池、洋上風力、M&A、原子力など幅広いトピックについて議論します。再生可能エネルギーの導入拡大が進む中で、日本のエネルギー・トランジションがどこまで進んでいるのか、そして今後どのような展開が期待されるのかを、多角的な視点から探っていきます。

AMT/ Innovation in Action:ナレッジ・マネジメントがもたらす新たな価値~門永真紀弁護士、 Financial Times主催Asia-Pacific Innovative Lawyers Award / Legal Intrapreneur賞受賞
AMTは、「Your Partner for Innovative Challenges」という理念を掲げ、多様な専門性を活かし、クライアントの課題解決に向けた革新的なアプローチを追求しています。この理念を象徴する出来事として、2025年5月15日、門永真紀弁護士が同年のFinancial Times主催「Asia-Pacific Innovative Lawyers Award」においてLegal Intrapreneur賞を受賞しました。この受賞は、同弁護士がナレッジ・マネジメントを通じてAMTの業務を変革し、法律業界全体に革新をもたらしたことへの高い評価を示しています。

座談会:エネルギー・トランジションの最前線【第2回】国内再生可能エネルギー市場の最新動向-太陽光発電を中心に-
前回のエネルギー分野に関する世界の潮流と日本企業の海外展開に続き、今回は国内の再生可能エネルギー市場、特に太陽光発電の最新動向についてお届けします。本記事では、コーポレートPPAの定着やFIP制度への移行など、市場の主要な流れを解説するとともに、法務面での課題や新たな事業展開の可能性についても専門的見地から分析します。
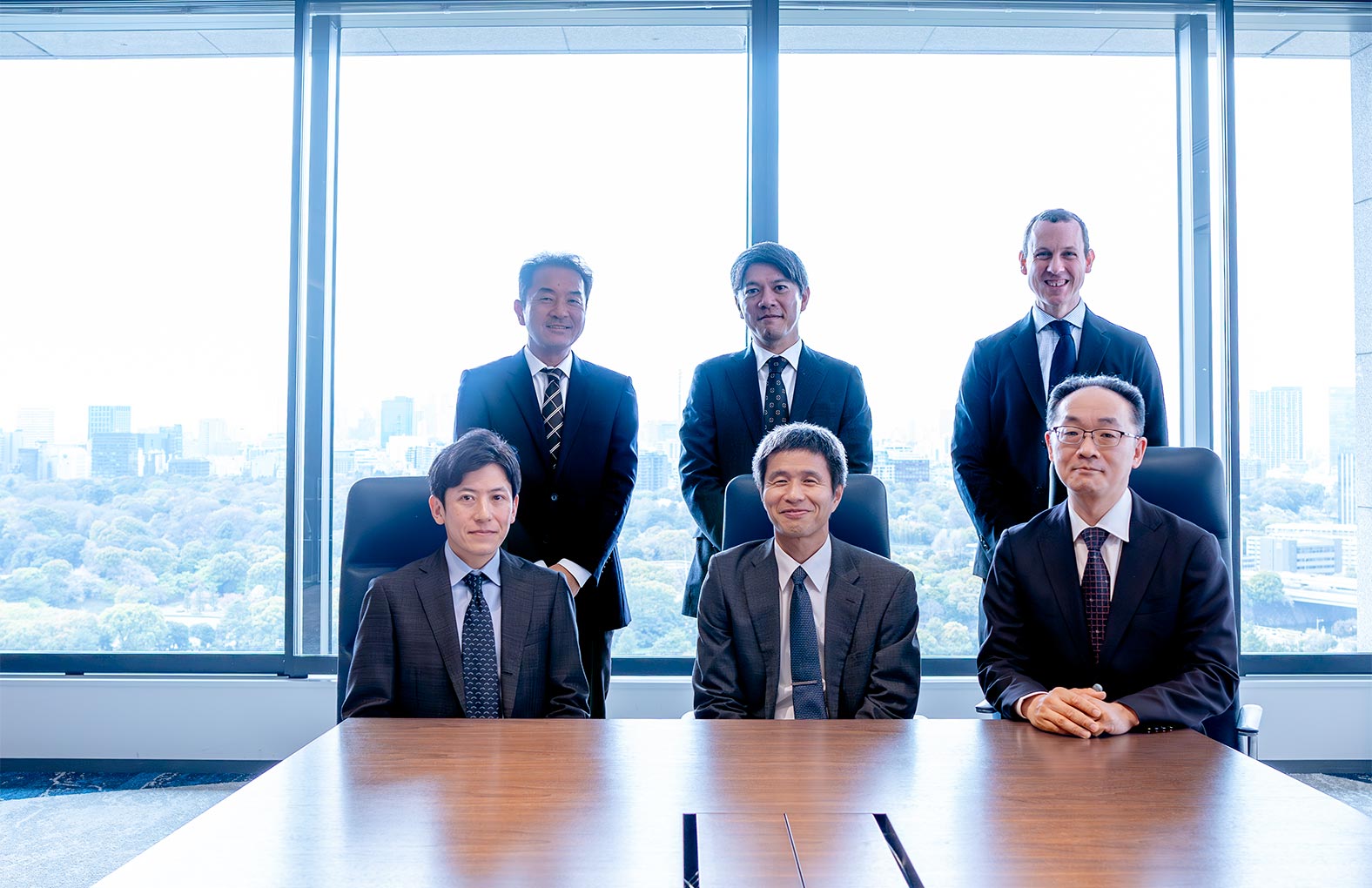
座談会:エネルギー・トランジションの最前線【第1回】エネルギー分野に関する世界の潮流と日本企業の海外展開
脱炭素社会の実現に向けた世界的な機運の高まりを背景に、クリーンエネルギー分野は急速に発展しています。本座談会では、クリーンエネルギー分野に精通した6名の弁護士が「エネルギー・トランジションの最前線」をテーマに、実務で直面する主要な課題や今後の展望について意見を交わしました。第1回は、エネルギー分野における世界のトレンドを整理した上で、市場の現状と日本企業の海外展開における課題に迫ります。

通商・経済安全保障分野の現代的問題点と経済インテリジェンスの重要性
WTOへの信頼が揺らぎ、自由貿易体制の動揺が見られる一方で、米中対立や地政学的リスクの高まりの結果、通商問題に安全保障の考慮が前面に出されるようになった。グローバルな企業活動の不確実性が増している中で、通商・経済安全保障の法務においては、経済インテリジェンスを集積し、幅と奥行きのあるアドバイスを引き続き提供していく。

エネルギー・トランジション法務と弁護士対談~実務最前線~
エネルギー・トランジションは、2050年カーボンニュートラル達成に不可欠なプロセスです。 本記事では、エネルギー・トランジション分野における当事務所の強みや豊富なサービスメニューをご紹介します。また、実務最前線の知識と経験を持つ弁護士たちによる対談記事も随時掲載し、エネルギー・トランジションに関する最新のホットトピックを深掘りしていきます。




