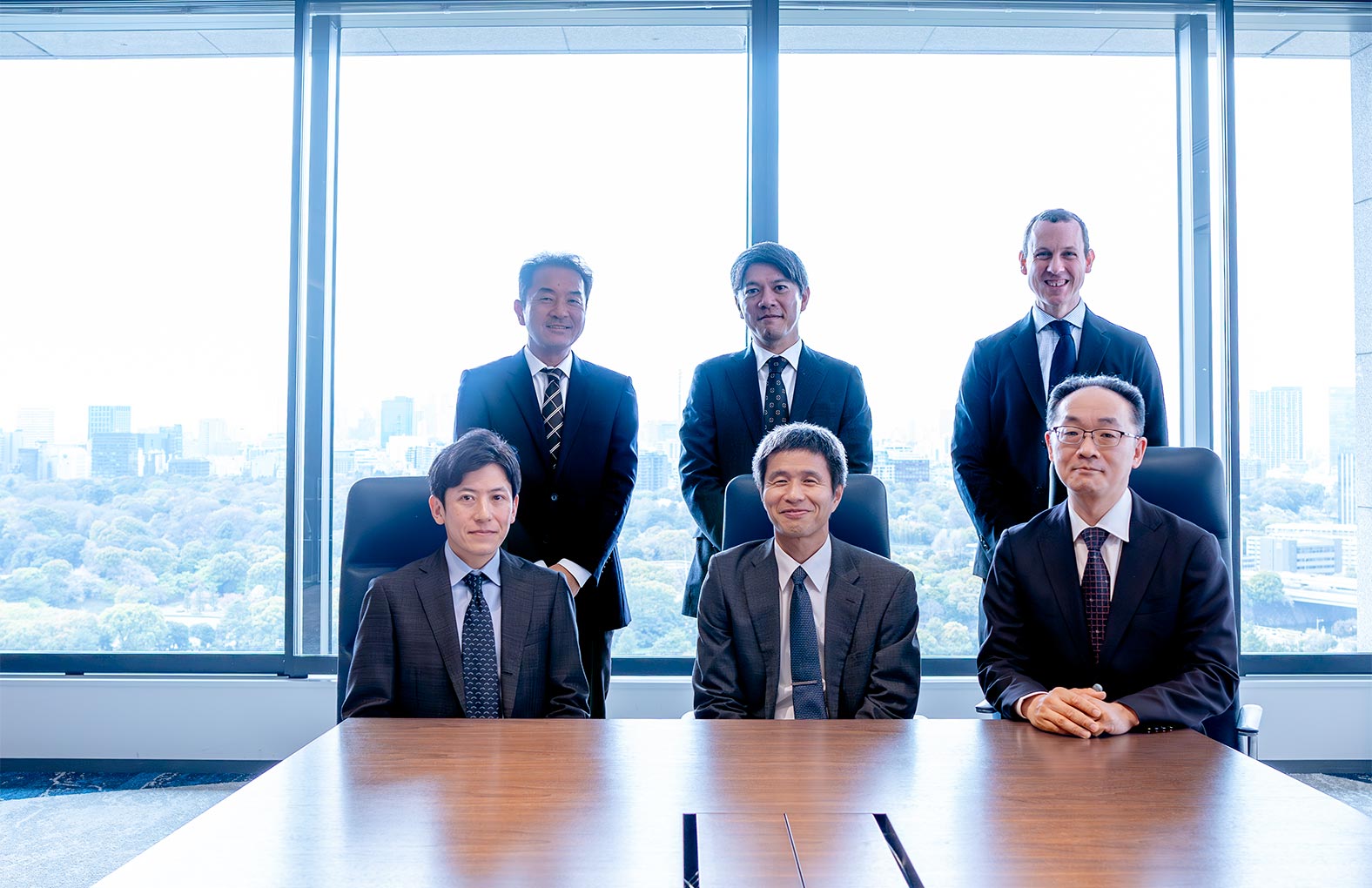前回のエネルギー分野に関する世界の潮流と日本企業の海外展開に続き、今回は国内の再生可能エネルギー市場、特に太陽光発電の最新動向についてお届けします。本記事では、コーポレートPPAの定着やFIP制度への移行など、市場の主要な流れを解説するとともに、法務面での課題や新たな事業展開の可能性についても専門的見地から分析します。
対談参加者
1. コーポレートPPAの定着とポートフォリオ取引の増加
武内 : 太陽光市場では、ここ数年で大きく二つの流れが見られます。一つは既設の太陽光ポートフォリオの売買案件の増加です。もう一つは、ポストFITとしてコーポレートPPAが珍しくないものとして定着しつつあることです。
前山
:
私は発電事業者側のカウンセルとして、コーポレートPPAやバーチャルPPAの黎明期から契約書作成を支援してきました。当初は手探りでしたが、現在は型もある程度定まり、実務としても取り組みやすくなってきたと感じています。
最近の新しい試みとしては、一般家庭の屋根に設置された太陽光発電設備を数千件単位のポートフォリオで買取り、プロジェクトボンドで資金調達するという日本初の案件をお手伝いしました。今後もこれに似た案件が増えるのではないでしょうか。

髙橋 : 太陽光発電のように案件が蓄積・累積してくると投資家が資金調達を工夫していき、プロジェクトボンドのような金融商品化するという流れになってきますね。
小林 : 私は海外投資家のカウンセルをすることが多いですが、昨今は海外投資家が保有する日本のポートフォリオを全て売却するというような案件も出てきており、今後も続くかと思います。
2. FIP転の増加と背景
髙橋 : 近時の太陽光の流れでいうと、FITからFIPに切り替える、いわゆる「FIP転」の動きが増えています。特に出力制御の時間帯が長い九州でこの流れが目立ちます。FIPでは、出力制御時間帯のプレミアムがその他の時間帯のプレミアムに上乗せされる調整ルールがあるため、出力制御を避けてプレミアムが高くなる時間帯に放電すると、より大きな利益を得られるからです。蓄電池を併設することで、このような運用が可能になります。
武内 : FIP転は今後も更に増えていくと予想します。その背景には、国による制度支援が大きく影響していると考えています。ご指摘のプレミアム調整ルールに加え、2026年度からは、FIP電源の出力制御の順番がFIT電源よりも後になるという施策が始まり、FIPに移行した方が出力制御を受けにくくなります。また、現在の施策がいつまで続くかは不透明ですが、FIP転蓄電池併設のための補助金制度も設けられています。こうしたFIP転を後押しする国の政策的な流れは、今後もしばらく続きそうです。

横井 : ファイナンスを想定した場合のFIP転した際の主な契約形態は、固定価格でのコーポレートPPAを締結してプレミアムを評価対象にしない方法と、プレミアム部分だけを評価するバーチャルPPAの方法がありますね。プレミアムはどう取り扱われていますか。
武内 : ファイナンスの観点からは、キャッシュフローの安定性が非常に重要です。既にプロジェクトファイナンスで資金調達がされている場合には、レンダーはFITの調達価格を基準にファイナンスしているので、少なくともコーポレートPPAの固定的な売電価格がそれと同等の水準にあると評価できることが、レンダーがFIP転を許容する条件になるものと思われます。FIPのプレミアムは市場価格に応じて変動するため、プレミアムまでを加味したキャッシュフローを評価してFIP転に応じるということは、現状ではレンダーにとってはハードルが高いように思います。
3. 規制対応の重要性
小林 : 太陽光発電に対する規制対応は、引き続き事業者にとって重要な案件管理上の課題の一つだと思います。最近の改正では、例えば事業計画の変更時に説明会の開催が義務付けられたり、廃棄費用の積立義務が導入されました。今後は太陽光パネルのリサイクル義務化に向けた制度設計も進む見込みで、こうした一連の動きは案件のライフサイクル全体にわたるコンプライアンス対応を求めるものです。再エネ分野は制度改正が頻繁に行われる領域ですので、規制変更への的確な対応という意味でも、法的アドバイスの需要の高さは今後も続くと思います。
4. 新しい事業展開の動き

横井 : 新しい動きとしては、ため池での水上太陽光発電があります。さらに珍しいところでは、洋上で太陽光発電を行うベンチャーも出てきています。技術的に容易ではないため採算性は課題ですが、注力している事業者もいます。陸上の適地が限られる中での新たな展開です。
小林 : 営農型太陽光も事業者から注目されており、技術開発が進んでいます。業界団体での会合でも度々話題として取り上げられていますし、今後は政府の後押しもあると思われますので、将来的には案件が増えるでしょう。
ハーン : 営農型太陽光発電は、地方での雇用創出や経済活性化を通じて、社会課題の解決にも寄与すると考えられます。農業従事者にとっては、収益源の多様化を図る手段となり、市場や気候の変動に左右されにくい、安定した経営につながる可能性があります。その結果として、耕作放棄地の減少にもつながるのではないでしょうか。加えて、生物多様性の保全にも役立ちますし、特に適地が限られていたり地価が高かったりする地域では、利用可能な土地の生産性を最大限に高める有効な手段ともいえるでしょう。
【おわりに】
今回は太陽光発電を中心に国内の再生可能エネルギー市場の最新動向をご紹介しました。コーポレートPPAの定着やポートフォリオ取引の増加、FITからFIPへの移行の加速、そして規制対応の重要性など、市場の主要な流れについてお伝えしました。特に蓄電池を併設したFIP転の動きは、今後のビジネスモデルとして注目すべき展開となっています。ため池・洋上・営農型といった新たな太陽光発電の展開についても、今後の動向に注目してきたいところです。次回は、蓄電池、風力、再エネM&A等の最新動向について取り上げる予定です。引き続きご期待ください。
関連コンテンツ
座談会:エネルギー・トランジションの最前線の第1回、第3回も、ぜひご覧ください。
-
本分野に精通する弁護士
 髙橋玲路ReijiTakahashi東京パートナーストラクチャードファイナンスを中心とした、金融業務を主要な業務分野としています。特に、PFIその他のプロジェクトファイナンス案件を多数行い、 PFI では国、公共団体のアドバイザーを務める他、金融機関、スポンサーのアドバイザーとしても多数の案件に関与しています。そのほか、インフラ・ファイナンス、水道事業その他の各種公益事業に関する民活又は民営化案件、各種ファンドの組成、海外プロジェクト案件等に従事しています。
髙橋玲路ReijiTakahashi東京パートナーストラクチャードファイナンスを中心とした、金融業務を主要な業務分野としています。特に、PFIその他のプロジェクトファイナンス案件を多数行い、 PFI では国、公共団体のアドバイザーを務める他、金融機関、スポンサーのアドバイザーとしても多数の案件に関与しています。そのほか、インフラ・ファイナンス、水道事業その他の各種公益事業に関する民活又は民営化案件、各種ファンドの組成、海外プロジェクト案件等に従事しています。 前山信之NobuyukiMaeyama東京パートナー各種ファイナンス取引(不動産・債権流動化、買収ファイナンス、CMBS(Commercial Mortgage-Backed Securities)、プロジェクト・ファイナンス(PFIを含む。)等)、コンプライアンス、企業買収(MBO案件を含む。)、民事再生申立等の倒産・事業再生案件、その他一般企業法務を主に手がけています。
前山信之NobuyukiMaeyama東京パートナー各種ファイナンス取引(不動産・債権流動化、買収ファイナンス、CMBS(Commercial Mortgage-Backed Securities)、プロジェクト・ファイナンス(PFIを含む。)等)、コンプライアンス、企業買収(MBO案件を含む。)、民事再生申立等の倒産・事業再生案件、その他一般企業法務を主に手がけています。 小林英治EijiKobayashi東京パートナー不動産開発、再生可能エネルギー関連プロジェクト、ファンド組成、プロジェクトファイナンス、開発関連紛争・訴訟等を含む大規模なプロジェクトに関連する法務を幅広く取り扱っており、国内・海外を問わず、投資家、開発業者、メーカー、デベロッパー等の多岐にわたる顧客にアドバイスしています。また、アジア・新興国関連案件も取り扱っており、特にロシアにおける合弁事業、投資案件等に対する助言について豊富な経験を有しています。
小林英治EijiKobayashi東京パートナー不動産開発、再生可能エネルギー関連プロジェクト、ファンド組成、プロジェクトファイナンス、開発関連紛争・訴訟等を含む大規模なプロジェクトに関連する法務を幅広く取り扱っており、国内・海外を問わず、投資家、開発業者、メーカー、デベロッパー等の多岐にわたる顧客にアドバイスしています。また、アジア・新興国関連案件も取り扱っており、特にロシアにおける合弁事業、投資案件等に対する助言について豊富な経験を有しています。 武内則史NorifumiTakeuchi東京パートナープロジェクト・ファイナンス、アセット・ファイナンス、コーポレート・ファイナンス、証券化等の金融法務及び企業買収等の会社法務を取り扱っています。また、再生可能エネルギーを中心としたエネルギー分野においては、プロジェクト開発、プロジェクト・ファイナンス、プロジェクト・ボンド、ファンド組成、M&A、紛争解決等、多岐の法分野にわたるサービスを提供しています。
武内則史NorifumiTakeuchi東京パートナープロジェクト・ファイナンス、アセット・ファイナンス、コーポレート・ファイナンス、証券化等の金融法務及び企業買収等の会社法務を取り扱っています。また、再生可能エネルギーを中心としたエネルギー分野においては、プロジェクト開発、プロジェクト・ファイナンス、プロジェクト・ボンド、ファンド組成、M&A、紛争解決等、多岐の法分野にわたるサービスを提供しています。 横井邦洋KunihiroYokoi東京パートナー国内・国外のエネルギー・インフラ案件、プロジェクト・ファイナンス等のファイナンス関連取引、PFI/PPP、建設案件、海外プロジェクト案件等を主要な業務分野としています。特にエネルギー・インフラ案件では、国内外への出向やその後の実務での数多くの経験を通じて、リーガル・ビジネス双方の観点から、クライアントのビジネスを成功に導くための戦略的なアドバイスを行っています。 また、国内・国外を問わず多くの企業へ、各種企業間取引やコンプライアンス、紛争・危機管理対応など一般企業法務の様々なタイプの分野において助言を行っています。
横井邦洋KunihiroYokoi東京パートナー国内・国外のエネルギー・インフラ案件、プロジェクト・ファイナンス等のファイナンス関連取引、PFI/PPP、建設案件、海外プロジェクト案件等を主要な業務分野としています。特にエネルギー・インフラ案件では、国内外への出向やその後の実務での数多くの経験を通じて、リーガル・ビジネス双方の観点から、クライアントのビジネスを成功に導くための戦略的なアドバイスを行っています。 また、国内・国外を問わず多くの企業へ、各種企業間取引やコンプライアンス、紛争・危機管理対応など一般企業法務の様々なタイプの分野において助言を行っています。